夏休みの作文
「聞いただけでテンション下がる。」
「あーーー!地獄!」
「なんで、作文あるの~!?」
って、思うママが多いのではないでしょうか🙁
わたしも、
このワード、苦手です😅
でも、今年は大丈夫!!!
今年は、
新しい味方『AI』を活用して、
この難関を突破しましょう‼️
作文を作るときの、AI活用のポイント

AIに全面的に頼るのではなく、「うまく活用する」ことが大切✨
お任せではダメです・・・❌
AIに「作文、書いて!」と言っても
理想的でステキな作文は作ってはくれません。
内容やタイトル、伝えたいポイントなど
あらかじめ、AIに伝える情報は準備しましょう。
AIは、
適切に使えば、
私たち親子の強力な援軍となってくれます👩👧👦
「AIを使った!」と、アピールしないほうがいい・・・かも
残念ながら、
日本ではAIを活用している方が少ないので、
AIに対しての理解が進んでいません😔
「宿題に活用した」というと
良いイメージをもたれないでしょう。
中国では
半分以上の国民が活用しているのですが・・・😥
特に、
学校の先生達は警戒をされている印象です😎
美術の宿題も、ここ数年で
「必ず手書き」
「パソコンでも良いけど、無料素材は使用禁止」
など、
規制項目が多くなりました。
いろいろ面倒臭くなるので(笑)、
アピールはやめましょう😅
ただ、今は日本人が追い付いていないだけ💦
やがて、嫌でもAI活用の時代はやってきます。
そのための練習と思って、
夏休みにお子さんとチャレンジされてください💕
具体的な活用方法:2日で作文を完成させる戦略

それでは、AIを活用しながら、
わずか2日で
作文を完成させる具体的な方法をご紹介します💫
1日目:テーマ選びと大枠の設定

1.お子さんと一緒に、作文のテーマになりそうな出来事をピックアップ
【ポイント】
いきなり考え始めても、
お子さんから作文のネタはなかなか出てきません💦
日頃から、
お子さんに意識させておくことも大事です。
わが家の場合は、
作文にできそうなエピソードがあった場合は、
スマホのメモ機能に残しています📱
そして、作文のテーマを考える時に、
どうしても、
お子さんが思いつかない場合に、
「こんなことがあったよね~!」
などと
提案するかんじでアプローチしましょう😊
2.選んだテーマが起承転結の構成に合うか考慮します。また、入選狙いの場合は、学校の先生が好みそうな内容かを考慮して決定します
「〇〇を頑張りました!」だけでは、
作文として組み立てずらいです。
そこに、
お子さんの想いをどれだけ乗せていけるかが重要です👌
また、入選や特選を狙っている場合は、
日常の何気ない発見や思い、
大人が見逃しがちな内容だと、
先生からの共感がえられやすい気がします💗
3.大まかな作文の流れを決めます。このとき、お子さんが訴えたいこと(思い)を中心に組み立てていくことが重要です
【ポイント】
お子さんに、
「じゃあ、作文を書こうか。」とは言わないことです⚠️
多分、お子さんは、
それだけで、やる気が失せるでしょう😥
起承転結に沿って、
4段階の構成で
お子さん自身の意見や思いを書いてもらいます。
4つに分けた起承転結に、
お子さんの思いを書いてもらうという感じです。
ここは、親御さんが上手く誘導してくださいね😉

1日目のポイントとして、
ここまでは、
同じ日に作業してください❣️
テーマ選びから作業しているので
お子さんの頭の中には、
作文に関する思いやワードがあふれています💞
取り合えず、
ここで、全部出してもらいましょう!
この方法なら、
お子さんも比較的スムーズに取り組めるはずです。
2日目:AIの活用と仕上げ
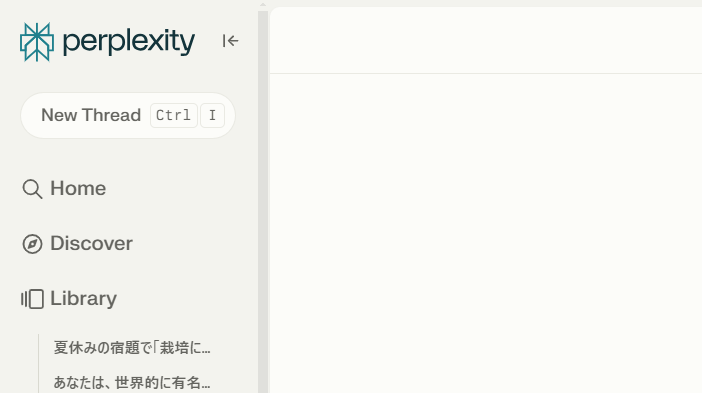
1.AIツール(Perplexity)に相談し、起承転結の内容について意見をもらいます
Perplexityは、
Googleアカウントなどで登録し、無料でも使えるAIツールです。
1分で完了するので、登録を済ませておいてください。
AIは、
どのような質問をするかが、とても大切です。
ユーザがAIに対して、入力する指示や質問のことを
「プロンプト」と言います。
私が実際に使用した
プロンプトをご紹介します。
質問例:
あなたはプロのwebライターです。
お願いしたいことがあります。
こどもの作文を作るのに、
まずは、タイトルと起承転結で文章をまとめてみました。
この時点での添削をお願いします。
修正点があれば、太文字で教えてください。
タイトル:〇〇〇
起:△△△
承:◇◇◇
転:■■■
結:▼▼▼
プロンプトは、
これが正解というものはありません。
逆に、私のプロンプトよりも
よりAIとのコミュニケーションが
スムーズなプロンプトもあると思います。
あくまでも、一例としてご覧ください。
2.AIからのアドバイスを参考に、必要があれば内容を加筆修正します
AIからの修正部分を、
お子さんと確認しながら修正、
または、
そのままで様子を見て作業を進めてください。
3.再度、AIに確認してもらい、OKなら指定の文字数で文章を作成してもらいます
再度、
AIに文章の確認をしてもらいましょう。
OKなら、指定文字数でまとめてもらいます。
質問例:
それでは、
1200文字で文章をつくってください。
4.AIが生成した内容を確認
【ポイント】
AIに任せると、
お子さんが体験していないエピソードや
事実と異なる内容が含まれる可能性があります。
そのような部分は、思い切って削除しましょう✂️
削除した部分は、
お子さんに新たな内容を考えてもらい加筆します。
【ポイント】
AIは、あくまでも補助です。
作文に、事実と違う内容や、
お子さんの気持ちではないことを
乗せることはオススメしません🙅♀️
お子さんに問いかけながら
お子さんの気持ちや
記憶を引き出してあげてくださいね😊
5.最終的な内容をAIに再確認してもらいます
質問例:
文章の修正がありましたら、
太文字で教えてください。
文字数は1200文字以内です。
今回、「太文字で教えてください」と
お願いしている場面が多いと思います。
ライティングの仕事であれば
AIに任せますが、今回はお子さんの作文です。
AIにお任せではなく、
どの部分にどういう修正が入ったのか
お子さん自身にも理解してもらうために
あえて、修正内容は太文字でお願いしています😉
6.原稿用紙エディタに入力し、印刷して完成です!
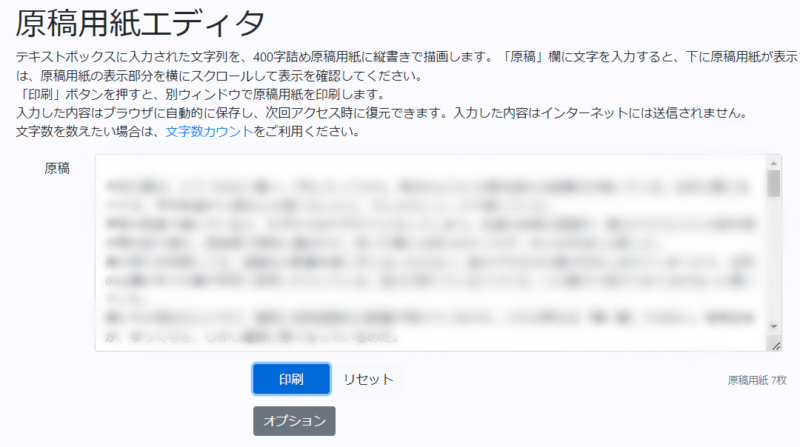
この、原稿用紙エディタとは、
文字入力するだけで
原稿用紙形式に変えてくれるサービスです💫
確認して、
問題がなければ印刷して出来上がりになります。
「手書きで提出」と決まっていない学校であれば、
こちらを利用するのがオススメです😊
夏休み作文をAIで活用するメリット

- 時間の節約:
従来なら何日もかかっていた作業が、
2日で終わらせられます。 - ストレス軽減:
親子ともに、
作文に対する負担が軽減されます。 - 学習機会の創出:
AIの使い方を学ぶ良い機会となります。 - 質の向上:
AIのアドバイスにより、
より構造化された読みやすい作文が作成できます。
最後に

AIを、
上手に活用することで、
夏休みの宿題に関する親子のストレスを
大幅に減らすことができます🤗
さらに、
AIを適切に使用する方法をお子さんに教えることで、
将来的に
役立つスキルを
身につけさせることができるでしょう✨✨
ただし、最終的には、
お子さん自身の経験や
考えが中心にあることを忘れないでください。
AIは私たちの手助けをしてくれる道具であり、
子どもの創造性や個性を置き換えるものではありません
AIをうまく活用して、
今年の夏休みを
親子ともに楽しく、
そして実りあるものにしましょう🍉🏝️👩👧👦



コメント